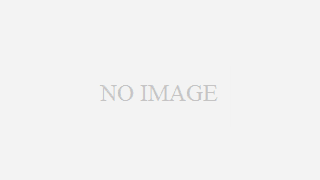〜菖蒲と浄化のスピリチュアルな意味〜
5月5日といえば「端午の節句」、そして「こどもの日」としておなじみですね。
鯉のぼりや兜飾り、菖蒲湯など、男の子の健やかな成長を願う日として知られています。
でも実は――
もともとの端午の節句は、女性のための“浄化の日”だったことをご存知でしょうか?
今回は、その由来とスピリチュアルな意味を、やさしく紐解いてみたいと思います。
■ 古代の端午は「女性の厄払いの日」
端午の節句の起源は、古代中国の「邪気払い」の習慣にさかのぼります。
旧暦の5月は、一年の中でもとくに気が乱れやすい時期とされており、
毒気(邪気)を払うために薬草を用いた儀式が行われていたのです。
この風習が日本に伝わると、平安時代には宮中の女性たちが5月5日に
• 菖蒲やヨモギで身を清め
• 神聖な香りで邪を祓い
• 心身をリセットする「五月忌み(さつきいみ)」を行っていました。
つまり、端午の節句はもともと「女性が自らを浄化する日」だったのです。
■ なぜ「男の子の節句」になったのか?
それが大きく変わったのは、鎌倉〜室町時代にかけての武家社会です。
• 「菖蒲(しょうぶ)」という言葉が、「尚武(しょうぶ=武をたっとぶ)」に通じる
• 菖蒲の葉が剣に似ていて、武の象徴とされた
こうした背景から、武士の間で“男児の厄除けと出世祈願”の行事として広まっていきました。
江戸時代には、庶民の間にも広がり、
• 鎧や兜を飾る
• 鯉のぼりを立てる
などの風習が定着。男の子の健康と成長を願う「男児の節句」として定着していきます。
■ 現代のスピリチュアルな視点で見る端午の節句
スピリチュアル的に見ると、端午の節句は次のようなテーマを持った特別な日です。
◎ 浄化と再生のタイミング
菖蒲やよもぎの香りは、氣(エネルギー)の浄化・邪気払いに使われてきたもの。
この時期に「菖蒲湯」に入るのは、単なる伝統ではなく、魂のリセットにもつながる古の知恵なのです。
◎ 陰陽のバランスを整える日
5月5日は「五」が重なる強い陽の日。
本来は、女性が内にこもった陰の氣を調え、陰陽バランスを整える日でもありました。
現代の私たちにとっても、
• 自分のエネルギーを整えたいとき
• 気持ちを切り替えたいとき
にぴったりのタイミングです。
■ 端午の節句におすすめのスピリチュアルアクション
ここでは、現代でも取り入れやすい過ごし方をいくつかご紹介します。
◎ 菖蒲湯に入る
香りを吸い込みながら、心身の「気」を整えましょう。
できれば「今日は自分を守る日」と意識して、お風呂に入る時間を大切に。
◎ 空間の浄化をする
菖蒲やよもぎが手に入らなくても、
• セージのスマッジング
• 風通しのよい場所での深呼吸
• 軽い掃除や断捨離
などで、空間と自分のエネルギーをクリアに整えましょう。
◎ 自分に「ありがとう」を伝える
この日はもともと「女性の心身を労わる日」。
性別を問わず、自分に感謝とねぎらいの言葉を贈ることもおすすめです。
■ おわりに
端午の節句は、ただ「男の子の日」ではありません。
本来は、季節の邪気を払い、命と暮らしを守る祈りの日でした。
あなたもこのタイミングに、
• 少しだけ立ち止まり
• 自分の心と体に「ありがとう」を言い
• これからのエネルギーを整えてみませんか?
静かに自分を癒す、そんな時間こそが、
本当の意味での“節句”なのかもしれません。